理想の転職先が見つかった時、あるいは会社に耐えられず仕事を続けられない時。
退職を決心した人にとって最後の関門となるのが『退職手続き』です。
サッと辞表を書いて仕事を整理したらさようなら…
そう簡単にはいきません!
辞表を提出してから退職までは1〜2ヶ月程度が一般的ですが、退職に関する事務手続きは結構面倒!
会社を辞めるのが初めての方は、必ずと言っていいほど戸惑います。
逆に、私が2社目の企業を退職する時は、慣れっぷりに総務のお姉さんが戸惑っていましたね苦笑
退職手続きはプロセスが多いものの、しっかしと把握しておけばすぐに対応できるものばかりです。
次なるキャリアへスムーズに進むために、退職手続きの基本と注意点を実体験を交えて解説していきます。
Contents
辞表提出から退職までの期間ってどのくらい?

辞意は1ヶ月前までに伝えよう
通常、退職手続きは、
- 直属の上司に辞意を伝える
- 辞表、退職願を提出する
- 仕事を引き継ぐ
- 人事、総務と退職関連の手続きを行う
- 退職
という流れです。
(1)の辞意表明から(5)の退職までの期間は、1〜3ヶ月程度であることが多いです。
私の場合は1社目では約2ヶ月、2社目では1.5ヶ月でした。
企業の就業規則では『退職は1ヶ月前までに申し出ること』と描かれていることがメジャーです。
パワハラや傷病など、特別な理由がない場合、就業規則に則って行動しましょう。
とはいえ、ある程度キャリアを積んだ方だと、仕事の引き継ぎを1ヶ月弱で終わらせることも難しいかもしれません。
普通の企業は中途採用者に『1ヶ月以内に入社しろ』と無理強いすることはありません。1ヶ月以内での入社を強要するようであれば、ブラック企業である可能性が限りなく高いです。
相手の会社や社員の都合を無視するような企業にロクな企業はありません。
エージェントや転職先と連絡を取りながら、無理なくスケジュールを組み立てましょう。
1ヶ月だと退職手続きだけでいっぱいいっぱいになりがちですからね。
2週間で退職出来るって本当?
民法上は退職願・退職届の提出から14日後に退職することが可能です。
就業規則よりも民法の方が優位ですから、2週間で退職しても何の問題もありません。
ハラスメントや病気など、会社にいることで症状が悪化する場合や、労働基準法を無視しているブラック企業など、会社に明らかに責任がある場合は、出来る限り早く退職することを考えましょう。
ただし、単純にキャリアアップ、キャリアチェンジを目的としている場合、円満に退職する方法を取りましょう。
同じ業界の企業や社員は全て横で繋がっています。
私は、転職先を誰にも伝えずに退職したのですが、転職先で、
『 A社から来たんだ!私、研究所のS君と大学の研究室一緒なの!』
と初日に言われ、その後すぐに前職の人たちに伝わってしまったことがあります。笑
民法を盾に引き継ぎもしないまま有給だけ消化して退職することは可能です。
ただし、その場合『無責任な人材』という噂は転職先にも必ず伝わると覚悟して行動しましょう。
前職でのコネクションやツテもあなたの大きな武器です。
無駄に自分の武器を捨ててしまうことが自分のキャリアにどんな影響を及ぼすか良く考えましょう。
有給消化も退職スケジュールに入れること
企業で半年以上勤務した場合、有給休暇を取得できます。
数年間勤務していると、有給が1ヶ月以上余っている人も多いのではないでしょうか。
有給はしっかりと消化して、旅行や家族サービス、帰省など、リフレッシュしてから次のキャリアに進みましょう。
退職は月の末日付がベター
退職日の設定ですが、基本的には月の末日をオススメします。
健康保険と厚生年金を初めとした社会保険関連は月末〆となっています。
月末の1日前に退職すれば、社会保険料を引かれずに最終月の給料を貰うことが可能ですが、デメリットが多いことに注意しましょう。
健康保険に関しては、1日でも未加入期間があれば役所で加入手続きする必要がありますし、厚生年金の加入期間も1ヶ月少なくなってしまいます。
企業は被雇用者の様々な金銭的負担を肩代わりしてくれています。
目先の小銭に捉われず、税金や賞与の計算期間など、総合的に判断して退職日を決めましょう。
退職に関する事務手続き

退職関連の主な事務手続き一覧
退職時に必要な返却物、書類は以下の通りです。
忘れている物がないか確認しておきましょう。
- 辞表(退職願・退職届)
各企業にテンプレートがある場合が多いです。無い場合でも特に形式はありません。常識の範囲内で作成しましょう。
上司に辞意を伝えた後、然るべき部署に提出します。記述の通り、1ヶ月以上前の提出が基本です。 - 健康保険被保険者資格喪失証明書
健康保険の移管には、この資格喪失証明書と印鑑が必要です。
退職から1日でもブランクがある場合、役所で健康保険の加入手続きが必要です。退職の1週間前になっても届かない場合、担当部署に問い合わせましょう。 - 雇用保険被保険者離職票(離職票)
退職後10日以内に会社から届きます。届かない場合は会社に問い合わせましょう。会社が発行してくれない場合は罰則がありますので毅然と対応しましょう。
ハローワークでの失業手当の手続きに必須の書類です。 - 源泉徴収票
年末調整は12月末日に在籍していた会社が手続きしてくれます。転職先に提出が必要ですので紛失しないようにしましょう。
また、年末までに再就職せず、自分で確定申告する場合にも必要です。
最後の給与計算が終わった後に発行するため、退職後に受け取る場合が多いです。私の場合は離職票と共に届きました。 - 年金手帳
通常は企業に預けてあるはずです。忘れずに受け取りましょう。 - 通勤定期
退職日付で清算します。キャッシュバックされた分を支払う、あるいは最終給与から天引きされる場合が多いです。 - 退職後の連絡先
退職後の書類送付等に使用します。基本的な個人情報を記入する書類を書くことになります。 - 誓約書
『企業の機密情報を漏洩させない』等の誓約が書かれた書類にサインします。内容に注意した上でサインしましょう。 - 社章、社員ID
悪用を防ぐために退職日に会社に返却します。
社員証や社章を紛失した場合、金銭負担となる場合が多いです。就業規則を確認しましょう。社員証明となるこれらのアイテムの価値は重いのです!
会社独自の福利厚生にも要注意!
どの会社にも共通の手続きを書いていきましたが、忘れがちなのが、その会社独自の福利厚生に関する手続きです。
- 確定拠出年金
- 福利厚生サービス(お得な旅行や観光地クーポンなど)
- 医療保険や車両保険の社員割引
- 従業員専用の持株制度
- 従業員専用の銀行口座
このような福利厚生の退会、移管手続きにも結構時間が取られます。
一部の福利厚生に関しては、退職後もOB扱いで継続できる場合があるので、確認しておきましょう。
大企業の福利厚生ウマー(^p^)
その分、退職後に恩恵を実感することも…
取引先への連絡も忘れずに
在籍中にやりとりのあった取引先にも忘れずに連絡しましょう。
営業活動などを通じて人として評価して頂いていた場合、前職の取引先は退職後も力になってくれます。
在籍中の会社から良い顔はされませんが、取引先を通じて別の仕事を紹介してもらったり、引き抜かれたりするパターンも多いです。
また、退職届の提出や退職日の決定は転職先に、転職エージェントを利用している場合はエージェントに忘れずに伝えておきましょう。
本当に入社してくれるのか、退職手続きがスムーズに進んでいるか…転職先の企業も不安なのです。
仕事で貰った名刺はどうする?
退職とともにその会社の社員ではなくなるわけですから、自分の名刺は全て返却します。退職後に使用すると身分詐称になります。トラブルの元ですよ!
また、業務を通じて頂いた名刺の所有権は、基本的に所属する会社に帰属します。
会社から申し出があった場合は直ぐに返却しましょう。
個人情報の取り扱いは社会人が最も注意すべきことです。
退職後も取引先とやりとりがある場合は、新しい名刺とともに再度交換しましょう。
『以前の名刺は会社に返却しました』と正直に話せば、ビジネスマナーとしても全く問題ありません。
退職後にやるべきこと
退職後にブランクが生じる場合、各手続きを自分で行う必要があります。
退職後に必要な手続きの概略を以下にまとめますので、該当者はチェックしておきましょう。
失業保険・傷病手当金の手続き
【失業保険】
退職後にブランクがある場合は、ハローワークに行き、失業手当給付を申し込みましょう。離職票を忘れずに!
自己都合退職の場合、失業保険は退職日から遡って2年間の間に、雇用保険に1年以上加入していることが必須条件です。
受理されてから3ヶ月は給付制限期間となり、手当は受け取れません。3ヶ月後から支払いが開始されますが、制限期間の3ヶ月分が支払われるわけではないので注意しましょう。
倒産やリストラなど、やむを得ない事情で退職した特別資格受給者は制限期間が発生しません。
【関連サイト】ハローワークインターネットサービス:雇用保険手続きについて
【傷病手当の継続】
鬱などで退職せざるを得ない人もいます。
すぐに復職できないこともあるでしょう。
退職日に傷病手当の基準を満たしており、1年以上の健康保険加入期間がある場合、退職後に残りの傷病手当を継続して受け取ることができます。
失業手当とは両立できませんが、退職後に傷病手当を継続する場合、失業手当の受取日を延長できるので、退職後1ヶ月以内に延長手続きしましょう。
【関連サイト】全国健康保険組合:傷病手当金について
国民年金と健康保険の手続き
退職翌月から、国民年金と健康保険が自己負担となります。
健康保険に関しては、任意継続と自己負担のどちらが安いか事前に確認しておきましょう。
退職して14日以内に居住地の役所で手続きを済ませましょう。
健康保険被保険者資格喪失証明書と印鑑を忘れずに!
通常は国民年金と健康保険の手続きを同時に行うことができます。
私の場合、退職に伴い社宅を出て一時的に実家に戻ったので、住民票の移管手続きも同時に済ませました。
面倒な手続きは一気に終わらせましょう。
【関連サイト】日本年金機構:退職後の年金手続きガイド
おわりに
退職という作業は本当にエネルギーを浪費します。
次の会社が期待に満ちたものであっても、あるいは会社が嫌いで一刻も早く辞めたい場合でも、退職決定から退職日までは疲れることが多いでしょう。
ポジティブな変化だったとしても、環境が変わり続けると大きなストレスになるものです。
有給を消化するなりして、リフレッシュして新しいキャリアに進めると良いですね。
退職までの期間も自分の重要なキャリアの一部です。
手を抜かずにスマートに終わらせましょう!
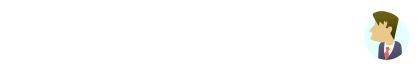
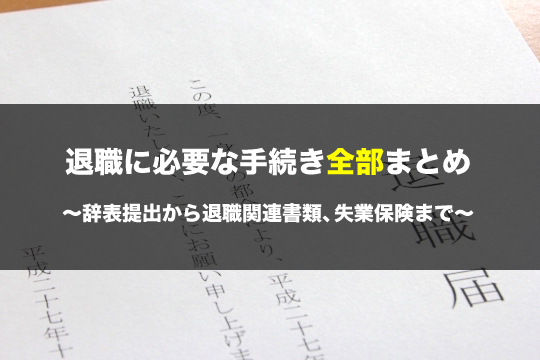
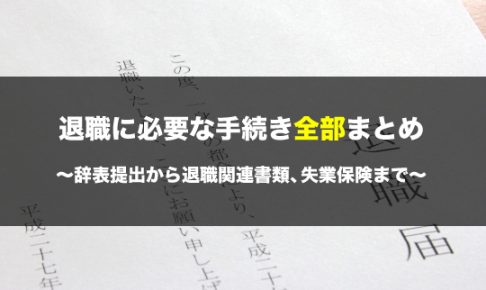


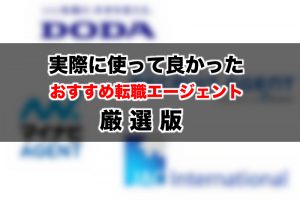
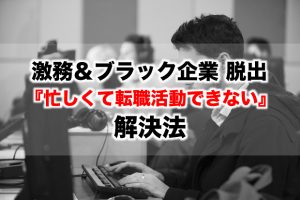

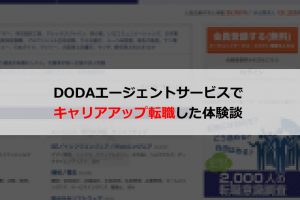
フォローする